戦争が起きれば、武器商人が儲ける - 朝鮮戦争特需
ネットと電波塔の情報戦争、もうけるのは、武器商人である - ウイルス対策会社
だれが、ウイルスをばらまいているんでしょうね?
ウイルス対策会社も怪しい - だよね? 儲かるもんね?
漁夫の利を得るのは、武器商人である - 濡れ手に、泡・・・
キャッシュフローを追え - ハーバード・ビジネススクール
戦争とは? 敵に勝って、なおかつ、戦費以上を略奪しなければ、損である - アメリカのイラク戦費は300兆円
金融危機で、失われたマネーは? 3000兆円、つまり、金融原爆が10発くらい破裂した・・・
これも、ウイルスの一種、非生産的暴徒
ウイルスでない人は? 赤尾敏さんです・・・
少なくても、選挙に立候補して、自身の思想信条を主張していた・・・
---Wiki
略歴 [編集]
アナーキストから国家社会主義者へ [編集]
少年時代は空想好きで、高等小学校に入学した時に教師から「太閤秀吉はぞうり取りから天下を取った」と言われ「俺だって勉強すれば総理大臣になれる」との夢を抱いたという。
旧制愛知第三中学(現在の
愛知県立津島高等学校)に進学後、
結核を患う。療養のため親元を離れ
三宅島に移る。そこで小説家・
武者小路実篤が唱えていた
新しき村運動(
原始共産制の実現を目指
した社会運動)の実践を志し、
実業家であった父から三宅島の牧場の経営を委ねられたという。
貧困の中にあった島の孤児らを引き取って共同農場を運営した。
農場では階級の別なく平等に作物が分配されるなどユートピア的な
制度が用いられ、「新しき村」運動に賛意を示していた小説家・
幸田露伴は赤尾の理想に共感して彼と面談している。またこの時に
三宅村神着地区の旧名主浅沼家とも知り合い、後に
日本社会党委員長
となる
浅沼稲次郎や
大日本愛国党参与となる
浅沼美智雄(
稲次郎とは遠縁になる)らとの交流が始まった。
赤尾は仲間らと共に理想的社会主義社会を建設する事を夢見たが、
農場は島の有力者らに騙し取られる。
苦い経験をしつつも
社会主義への展望を棄てず、東京の
左翼運動に
参加する。
アナーキズムの大家であった
大杉栄や後の
日本共産党書
記長
徳田球一らの支援を受け熱心に活動する。
軍事教練の最中に
天皇制への批判演説を行い身柄を拘束されたほか、
地元財界の有力者に活動資金のカンパを要求したことが恐喝未遂と
されて逮捕された。その際、それまで同志だと思っていた「
愛知通信」の記者から手のひらを返した様に批判されたことで、
左翼運動に深く失望した赤尾は獄中で
転向を決断する。
国会議員当選 [編集]
赤尾は獄中で
仏教、
儒教、
キリスト教などの書物を読む。
またメーデーに対抗するために「建国祭」を企画。「建国祭」は
荒木貞夫や
平沼騏一郎らの賛同を受け、
全国で12万人を集め成功に終わる。
赤尾は建国祭の常設機関として建国会を結成、書記長に就任する。
1942年の
第21回衆議院議員総選挙では東京6区から出馬し、
大政翼賛会の推薦を受けない「非推薦候補」ながら当選を果たす。
トップ当選であり、得票数は都内で2位、全国で4位だった。
鳩山一郎、
斎藤隆夫、
中野正剛、
笹川良一など他の非推薦議員と同様に
翼賛政治会(翼政)に加入はしたが、
1943年の第81通常議会
では戦時刑事特別法改正案に抗議し委員を辞職(
3月8日)。
また続く第82臨時議会では施政方針演説に臨もうとした
東條英機首相に対し議場退場処分(同年
6月16日)、翼政を除名され、
議会からも譴責の懲罰を下されるなど、
右翼ながら筋を通した反体制派議員としての行動が目立った。
なお、戦後国会内でのビラ撒きにより元
国会議員待遇を剥奪されて
いる(
当選無効ではないので、
国会議員であった事実が取り消されたわけではない。
選挙報道などでは、その後も「元議員」として扱われている)。
戦後 [編集]
配下の党員であった
山口二矢(事件当時は離党)が起こした
浅沼稲次郎暗殺事件では取調べを受け、
嶋中事件では
殺人教唆で逮捕され
ている(証拠不十分で釈放)。
沢木耕太郎『テロルの決算』
によると、山口は浅沼の「
アメリカ帝国主義は日
中両国人民の共同
の敵」発言に殺意を抱いたという(このことは本人の「斬奸状」
にも触れられている)。また、
赤尾が個人的に交流のあった浅沼を「善人だから始末に悪い」
と評したこともきっかけとなったのではないかとする。
事件後赤尾は浅沼の妻享子や
三木睦子と電話で連絡を取り合ったと
いうエピソードもある。
また、アメリカンアセンブリーと国際親善日本委員会が主催していた第二回下田会議の初日、長髪をなびかせ数人を引き連れてロビーに押し込もうとしたことがある。日の丸の旗を振りながらホテルに上がってきた赤尾は「共産主義の脅威と戦うために再軍備すべきだ」と主張したが、駆け付けた警察に逮捕された。
人物 [編集]
困窮の中でも
参議院選挙への立候補・落選を繰り返した。
第二次世界大戦前の左翼活動の中で感じた憤りから徹底して世の中の矛盾を
糾弾し、歯に衣着せない、
狂信的とも見えるが筋の通った演説は市井の零細企業経営者から与
党政治家まで幅広い支持者を得た。
また赤尾を取材したカメラマン・
宮嶋茂樹によると立会演説会の前
に控室で対立候補を罵倒するほか、
演説会が始まる直前に勝手に舞台の前に立って「君が代」
の斉唱を促し、
あわせて聴衆にまぎれた党員たちが立ち上がり伴奏なしで歌いだす
などの行動を取っていたという。
宮嶋は赤尾の行動が立会演説会が廃れた理由となっていると指摘し
ている。
自身を「
泡沫候補」扱いするマスコミに、
一貫して異を唱え続けた。
作家の
小田実は『
朝まで生テレビ!』に出演したとき、
赤尾について「私があちこちで演説すると、
必ず孤独な演説者が一人いたよ。赤尾敏だ。おれも(横で)
やっているわけ。どっちも聞いておらんよ、誰も。
それはひとつ変なつきあいだった」と語っていた。
長崎県佐世保港へ
空母エンタープライズが入港した時に抗議の演説
をすべく昭和40年(1965年)
1月31日に佐世保市へ出かけたところ佐世保市内で16歳の少年
が脇見運転するバイクに跳ねられるという事故に遭った。
しかし赤尾敏はその少年が仕事でバイクに乗っていた事を知ると「
16年の若さで仕事をしているとは感心だ」
として訴える事などしなかった。
没後「敵」であった
公安警察の一部から「
過激ではあったが至誠の人」という評価を得る反面、
味方のはずの右翼の一部からは「金にケチだった」、「
自分一人が目立ちたがった」
などの理由であまり好意を持たれていない。
著書 [編集]
- 『一切を挙げて赤露の挑戦に備へよ』(皇道パンフレット)(建国会出版部、1935年)
- 『日本の外交を何とするか』(建国会、1940年)
- 『滅共反ソか反英米か』(建国会、1940年)
- 『日米問題と日ソ関係』(建国会、1941年)
- 『憂国のドン・キホーテ』(山手書房、1983年)
参考文献 [編集]
- 終生のロマンチスト…………赤尾敏 p61~p81 〔初出:「赤尾敏一代記」 『新潮45』1990年4月号〕
関連項目 [編集]
外部リンク [編集]
内容(「BOOK」データベースより)
殺しつくし、焼きつくし、奪いつくす。中国の人びとから「日本鬼子」と呼ばれるような蛮行を、なぜ自分たちは犯したのだろう―。
やはり、鬼畜ニッポンだ・・・
三光原爆 - 広島、長崎、金融
とくに、一生懸命に講義を聞いたわけではない、というか、あまり出なかった・・・(東大教養学部)
だが、先生にはソウルがあった・・・
よって、一番大事なことだけが、残っている・・・
専門課程の高橋助教授は放任主義
学生の相手なんかしてられん、助手へ、やっとけ
これが大正解、助手の小林さんは御熱心
だが、体を壊したので、定時になったら、ご帰宅、一般消費税?導入反対派だった気がする・・・
そして、卒論の発表練習だけは、高橋助教授がご登場
最後の最後に、「実験物理学の原理」を教えてもらった。目からウロコとはこのこと。
ショーゲキ的だった・・・ 驚いた、頭の中の靄が晴れた・・・
そして、卒論発表・・・ 小林さんのコメントは?
あんたの発表は文学だ、大先生が居眠りしてたよ、笑い
卒論の成績は、優だった・・・
今、小林さんに反論する?
物理学は、とくに、理論物理学は、言葉でも、表現できます。
物理学は哲学です・・・
数式を使うのは、厳密化、簡略化のため・・・ 学会で発表するため、物理学者の共通言語が数式です
そして、理論を実証するのが実験。実験で立証されて、初めて、理論が承認される - 物理学会
壇ふみさんへ
ポルトガルへ行ったトキ、壇一雄の館を探しに出かけた・・・
細かい地図はなし・・・ ローカル線に乗って、町の人に尋ねながら・・・
近くまで来たようだったが、見つけられず・・・
そして、その辺りのカフェで、昼飯を喰った・・・
イワシの塩焼きはポルトガル(リスボン?)名物です・・・
壇一雄の料理の本があったはず・・・
火宅の人は? 家族をいかにして料理するか? じゃなかったっけ? ふみさん?
捌いたり、捌かれたり、まないたの鯉、恋?
同じ壇でも、檀違いでした、悪しからず - 仏壇、紫檀、黒檀
1.
21時間以内に「お急ぎ便」でご注文いただくと、2010/7/26 月曜日までにお届けします 。
通常配送無料
2.
21時間以内に「お急ぎ便」でご注文いただくと、2010/7/26 月曜日までにお届けします 。
通常配送無料
3.
21時間以内に「お急ぎ便」でご注文いただくと、2010/7/26 月曜日までにお届けします 。
通常配送無料
想いだした・・・
リスボンの丘の上、ケーブルカーで古い街並みへ・・・
ガンバスとワイン
音楽は? ポルトガルの悲哀、何だっけ? ファド、ファド酒場
ワインが、ダン(Dao)でした・・・ ブランコは白、赤は何だったっけ?
赤のダンでした・・・ ティントだった・・・
■ポルトガルワインの歴史
ポルトガルワインの歴史は古く、紀元前5世紀にはフェニキア人によってブドウ栽培が始められました。8世紀から11世紀まではイスラムの支配により一時停滞しますが、キリスト教徒が領土を回復してから再びワイン造りが盛んになりました。12世紀にスペインから独立してからもワイン造りは行われ、伝統的な栽培法や醸造法をもとに近代的醸造技術を採り入れることによりポルトガル固有のワインを造りあげてきました。17世紀にはマデイラワイン、18世紀にはポートワインが登場し、これらはスペインのシェリーと並んで世界三大酒精強化ワインと呼ばれています。
また、ポルトガルは歴史的に日本との繋がりが深く、16世紀の半ばにヨーロッパから初めて日本に訪れたポルトガル人によって、キリスト教や鉄砲とともにワインが伝えられました。ポルトガルワインはポルトガル語で赤ワインを意味するTinto(ティント)から「珍陀(ちんた)」と呼ばれ、戦国時代の武将も珍重したと言われています。
最近では、昭和の文豪、壇一雄氏(壇ふみ(女優)さんの父)が氏の姓と同じ発音のダンワインを愛飲されたことでも知られています。氏はポルトガルに1年4ヶ月間滞在し「火宅の人」を執筆されましたが、その間「赤、白のダンワインを何百本抜いたことか」と随筆に記述するなど、ダンワインへの特別な思い入れがあったことが伺われます。
■注目のワイン産地、ポルトガル
「今、最も注目されるワイン産地」、ポルトガルワインをジャンシス・ロビンソン始め世界の著名なワインライター達はこう表現します。紀元前5世紀頃からワイン造りの歴史を誇るポルトガル。近世、ワイン産地を捜し求める英国人がこの地でポートやマデイラの酒精強化ワインを生み出し、1900年パリ万博ではダンワインが金賞を受賞、一躍ヨーロッパで注目されるようになりました。
しかしながら20世紀の中盤以降、サラザール独裁政権の下、半鎖国のような状態が続き、ポルトガルワインはそのほとんどが国内で消費されていたため、この時期、ポートワイン、マデイラワインや一部のワインを除きポルトガル産のワインは国際的な舞台からは遠ざかっていました。1974年の「カーネーション革命」の後、1986年のEC(現在のEU)加盟を果たし、ポルトガルワインの市場は国内からヨーロッパそして世界に拡大されました。EU新規加盟国ポルトガルの産業基盤を強固にするために、EUとしてポルトガルの産業振興へ数々の支援を実施。ここで最も期待されたのはワイン産業でした。
ポルトガルの生産者たちの目の前に最新のワイン製造技術と大きな市場が広がりました。EUの経済的支援もあり、ここからポルトガルのワイン造りは激変します。もとより有史以来の長いワイン造りの伝統を持ち、国土のほとんど全ての場所でブドウが栽培され、個性あふれるワインを生産しているポルトガルに最新の醸造技術を学んだ新世代の造り手達が、EUのバックアップもあり次々と革新的なワインを生み出すに至りました。この状況はワイン消費国にも知れるようになり、最初は安くて美味しいワインの生産国として知られ、2000年以降は世界の銘醸ワインに勝るとも劣らない素晴らしいワインを生み出す産地として著名な評論家に認められるようになりました。
今や世界のワイン愛好家が次はどんなワインが出てくるかと、最も注目されるワイン産地に位置づけられるようになりました。
■ポルトガルのワイン生産について
ブドウ栽培面積:24万8000ha(世界第8位) 栽培されているブドウ品種:300~500種
ワイン生産量:約730万hl(世界第11位)-赤・ロゼワイン:54% 白ワイン:34% フォーティファイド・ワイン:12%
ワイン輸出量:世界第8位 1人当たりのワイン消費量:47L(ルクセンブルク、仏に次世界第3位、日本(2.5L))
■ポルトガルのワイン法
1756年、ドウロ地区(ポートワイン用ブドウ生産地域)に世界で初の原産地呼称管理法を制定。
1986年EUに加盟とともにEUワイン法に沿った整備がなされ、指定地域優良ワイン(V.Q.P.R.D.)の制度を設けて、全国のワイン産地を下記のように分類しています。 |
無告の民と政治 => 民主化の必要性、宗教の欠点
国際関係論 => バランス・オブ・パワー
昔の論だから、修正が必要なことは明らか
軍縮はビジネスチャンスである、だが、リスク回避のためにバランス・オブ・パワー - 政治経済力学
お布施やお賽銭は、余剰物のおすそわけ
収穫祭、豊作であれば、秋祭り - 神社
収穫祭、飢饉であれば、救貧院 - お寺
お寺や神社の箱モノだけがご立派 => 国を滅ぼす
祭りのための祭りも、ムリが大きく、民を滅ぼす、国も滅ぼす
だよね? スサノオ? お釈迦様?
Aoyagi YoSuKe
Creator
白い鷺を見かけた
おれおれ、詐欺ではない。
おれん、おれん、サギである・・・
おれは、ここには、おれん、おれんと言いながら、飛んでいく・・・
橋の下で、何かを喰っていた・・・ 土壌じゃねえよな?
| Click here to see in English. |
または
1-Clickで注文する場合は、 サインインをしてください。 |
|
|
|
|
あなたは「三光作戦」を知っていますか―日本にも戦争があった〈2〉 [単行本]
坂倉 清 (著),
高柳 美知子 (著)
商品の説明
出版社/著者からの内容紹介
【自分たちはなぜ、あんな残虐なことをしたのだろう---- 】坂倉清さんは、1940(昭和15)年から敗戦まで、
日本軍兵士として、
中国の人びとにたいし、殺人、放火、拷問、略奪など、
数え切れない残虐非道な罪を重ねました。
中国の人びとから「日本鬼子」と言われる蛮行を、
なぜ自分は犯したのか----
日本が再び同じ過ちを繰り返さないために、
自らの行為を赤裸々に告白します。
内容(「BOOK」データベースより)
殺しつくし、焼きつくし、奪いつくす。中国の人びとから「
日本鬼子」と呼ばれるような蛮行を、
なぜ自分たちは犯したのだろう―。
登録情報- 単行本: 157ページ
- 出版社: 新日本出版社 (2007/06)
|
---Wiki
経歴・人物 [編集]
1948年東京大学法学部政治学科卒業、1949年同大学院退学、
東京大学東洋文化研究所助手(1949-53年)。
東京工業大学理工学部助教授(1953-59年、1958年から併任扱い)、東京大学教養学部助教授(1956-67年、1958年まで併任扱い)、東京大学教養学部教授(1967-84年)を歴任。1984年東京大学名誉教授となる。
東洋文化研究所時代に
植田捷雄に師事。清朝末期の中国政治外交史研究からスタートし、国際関係論研究に進む。シミュレーションの活用、『
人民日報』の内容分析など当時米国の国際関係論研究で導入されはじめた先進的手法を用いた研究を行なう一方、論壇における活躍でも知られた。亜細亜大学学長時代に、いわゆる『一芸一能入試』や『正規単位取得型の留学プログラム(AUAP)』を導入し、制度化したことでも知られる。
門下生に
平野健一郎、
山本吉宣などがいる。また、直接の指導学生ではないが、
岡部達味は国際基督教大学助手時代、衛藤の元に通う「押しかけ弟子」であったと語っている。
賞詞 [編集]
社会的活動 [編集]
- アジア政経学会理事長(1978-1981年、1983-1985年)
- 財団法人アジア研究協会理事長
- 財団法人平和・安全保障研究所理事
- 財団法人女性のためのアジア平和国民基金副理事長
- 財団法人国際文化交換協会理事
- 社団法人日本スカッシュ協会会長
- 財団法人りそなアジア・オセアニア財団理事
- 日本戦略研究フォーラム理事
- 国立国会図書館納本制度調査会会長(1996年)
- 国会議員の秘書に関する調査会委員長(1991年)
- 財団法人日中友好会館 「日中友好岸関子賞」選考委員
著書 [編集]
単著 [編集]
- 『無告の民と政治――新生日本外政論』(番町書房, 1966年/新版 東京大学出版会, 1973年)
- 『近代中国政治史研究』(東京大学出版会, 1968年)
- 『東アジア政治史研究』(東京大学出版会, 1968年)
- 中国語訳『東亜政治史研究』(水牛出版社, 2000年)
- 『大世界史(20)眠れる獅子』(文藝春秋, 1969年)
- 『日本の進路』(東京大学出版会, 1969年)
- 『日本宰相列伝(22)佐藤栄作』(時事通信社, 1987年)
- 『学長の鈴――偏差値より個性値』(読売新聞社, 1988年)
- 『個性値教育のすすめ――くたばれ偏差値 偏差値病につかれた親に捧げる本』(ごま書房, 1989年)
- 『二流のすすめ――21世紀をになう者』(講談社, 1993年)
- 『近代東アジア国際関係史』(東京大学出版会, 2004年)
共著 [編集]
- (岡部達味・松本繁一・向山寛夫)『中華民国を繞る国際関係――1949-65』(アジア政経学会, 1967年)
- (岡部達味)『世界の中の中国』(読売新聞社, 1969年)
- (坂本二郎ほか)『大国日本の進路』(自由社, 1971年)
- (三好修)『中国報道の偏向を衝く――調査報告 自由な新聞の危機』(日新報道, 1972年)
- (篠原三代平)『世界政治・経済を見る眼』(世界経済情報サービス, 1978年)
- (公文俊平・平野健一郎・渡辺昭夫)『国際関係論(上・下)』(東京大学出版会, 1982年/第二版, 1989年)
- (許淑真)『鈴江言一伝――中国革命にかけた一日本人』(東京大学出版会, 1984年)
- (山本吉宣)『総合安保と未来の選択』(講談社, 1991年)
編著 [編集]
- 『アジア現代史』(毎日新聞社, 1969年)
- 『大国におもねらず小国も侮らず』(自由社, 1973年)
- 『国際社会における相互依存の構造分析』(世界経済情報サービス, 1977年)
- 『日本をめぐる文化摩擦』(弘文堂, 1980年)
- 『現代中国政治の構造』(日本国際問題研究所, 1982年)
- 『大学国際化への挑戦――亜細亜大学の試み』(サイマル出版会, 1993年)
- 『共生から敵対へ――第4回日中関係史国際シンポジウム論文集』(東方書店, 2000年)
共編著 [編集]
- (植田捷雄・魚返善雄・坂野正高・曽村保信)『中国外交文書辞典 清末篇』(学術文献普及会, 1954年)
- (坂野正高)『中国をめぐる国際政治――影像と現実』(東京大学出版会, 1968年)
- (内田忠夫)『新しい大学像をもとめて』(日本評論社, 1969年)
- (永井陽之助)『講座日本の将来(3)世界の中の日本――安全保障の構想』(潮出版社, 1969年)
- (宮下忠雄・佐藤慎一郎)『現代の世界(3)東アジア』(ダイヤモンド社, 1970年)
- (山陽新聞社)『日本の新しい進路――70年代への提言』(鹿島出版会, 1971年)
- (坂野正高・田中正俊)『近代中国研究入門』(東京大学出版会, 1974年)
- (浦野起央・嵯峨座晴夫)『戦後世界データハンドブック』(世界経済情報サービス, 1979年)
- 『日本の安全・世界の平和――猪木正道先生退官記念論文集』(原書房, 1980年)
- (井上清)『日中戦争と日中関係――盧溝橋事件50周年日中学術討論会記録』(原書房, 1988年)
- China's Rpublican Revolution, coedithed with Harold Z. Schiffrin, (University of Tokyo Press, 1994).
- (李廷江)『近代在華日人顧問資料目録』(中華書局, 1994年)
訳書 [編集]
- E・H・カー『両大戦間における国際関係史』(弘文堂, 1959年/清水弘文堂, 1968年)
- ジョン・K・フェアバンク『人民中国論』(読売新聞社, 1970年)
- ケネス・ボールディング『紛争の一般理論』(ダイヤモンド社, 1971年)
- 『毛沢東思想万歳(上・下)』(監訳, 三一書房, 1974-75年)
- 宮崎滔天, My Thirty-Three Years' Dream, the Autobiography of Miyazaki Toten, (Princeton University Press, 1982).
著作集 [編集]
- 『衞藤瀋吉著作集』(東方書店, 2003年-2004年)
- 1巻『近代中国政治史研究』
- 2巻『東アジア政治史研究』
- 3巻『近代アジア国際関係史』
- 4巻『眠れる獅子』
- 5巻『中国分析』
- 6巻『国際政治研究』
- 7巻『日本人と中国』
- 8巻『無告の民と政治』
- 9巻『日本の進路』
- 10巻『佐藤栄作』



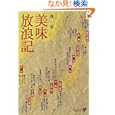
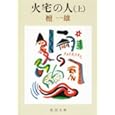


0 件のコメント:
コメントを投稿